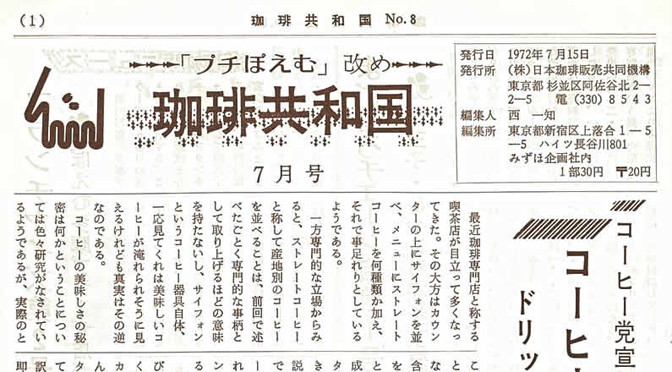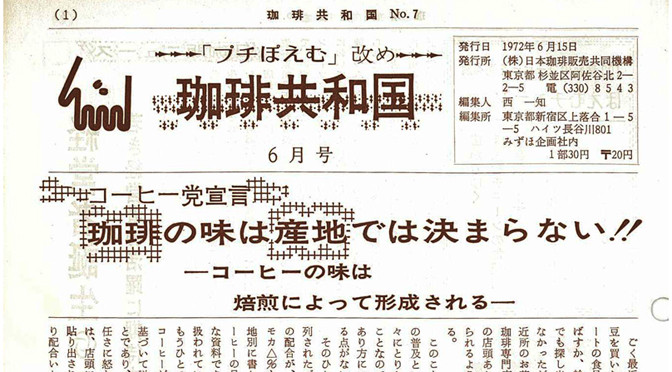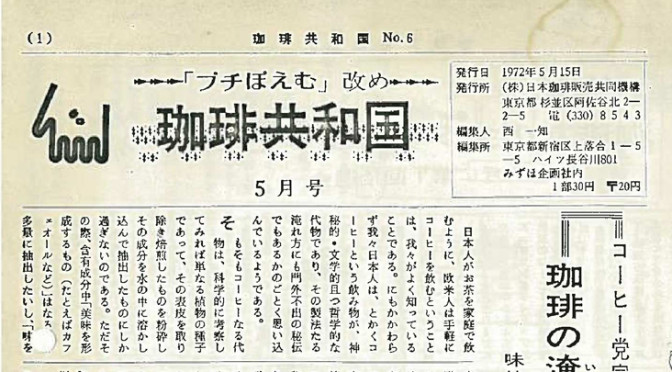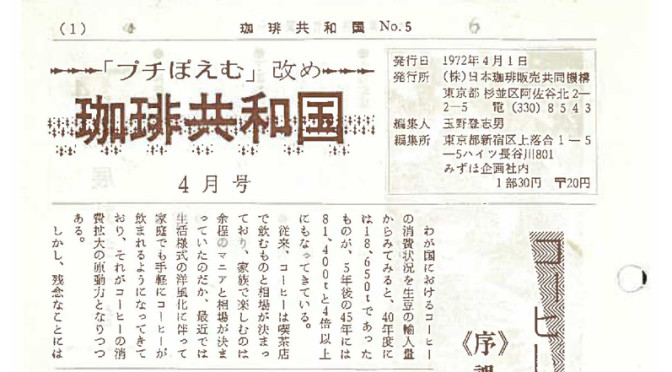1972年7月15日コーヒー党の機関誌「珈琲共和国」より

最近珈琲専門店と称する喫茶店が目立って多くなってきた。その大方はカウンターの上にサイフォンを並べ、メニューにストレートコーヒーを何種類か加え、それで事足れリとしているようである。
一方専門的な立場からみると、ストレートコーヒーと称して産地別のコーヒーを並べることは、前回で述べたごとく専門的な事柄として取り上げるほどの意味を持たないし、サイフォンというコーヒー器具自体、一応見てくれは美味しいコーヒーが淹れられそうに見えるけれども真実はその逆なのである。
コーヒーの美味しさの秘密は何かということについては色々研究がなされているようであるが、実際のところこれが決定的な真実だという結果は得られてはいない。しかし、コーヒーに含まれたカフェインが心身を爽やかにし、カフェオールという物質が香りや味を形成し、カラメル質や少量のタンニンがその味を更にひき立てているというのが定説となりつつある。その中で特に大事なのがカフェオールとカラメルが充分含まれるということであり、タンニン含有は少量にとどめることである。
カフェオール・カラメル及びタンニンは共に高温でよく溶けるが、カフェオール・カラメルは短時間中にほとんど溶出する。それに対しタンニンは、長時間に渡って抽出される。そのような訳で、コーヒーを淹れる、即ちコーヒー末より湯を用いてコーヒーの成分を取り出す場合は、高温な湯を短時間にコーヒー末に接触させることが必須条件であって、長時間に渡って煮るということなどはもってのほかである。ところが、サイフォンという器具はフラスコの中の湯が、フラスコ中の空気の膨張によって圧力がかかり、押し上げられるので、湯が低温であってもロートに上昇してしまうことが多い。
そのため、一番大切なときに好ましくない温度で湯と末が接触してしまうのである。この結果、カフェオール・カラメルの溶出は押さえられてしまう。その上、ロートのお湯は下からの射熱によってその後どんどん上昇し、カフェオールやカラメルの溶出に適する温度になるのだが、そのときは同時にタンニンの溶出もタップリなされてしまう訳なのである。故にサイフォンのコーヒーは見た目も不透明で、上質の赤ブドー酒の色をもって最上というコーヒー本来の色にはほど遠く、味もタンニンが多いために渋みが強くて多量に飲むと吐き気をもよおすのである。
それに反して、ドリップ法は、湯とコーヒー末の接触温度や時間を手軽にコントロールすることができるので、常に理想的なコーヒーが得られるのである。
珈琲専門店の本来の機能は、上質の珈琲豆や正しい知識を提供するものであって、決して見てくれやハッタリで客を引くためのものではないのである。すなわち、今、巷間に続々生まれつつある珈琲専門店と称する喫茶店は、純喫茶・音楽喫茶・ヌード喫茶など新手の喫茶店のひとつであって、珈琲専門店とは縁もユカリもないものなのである。